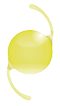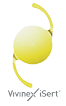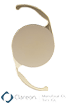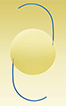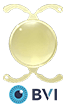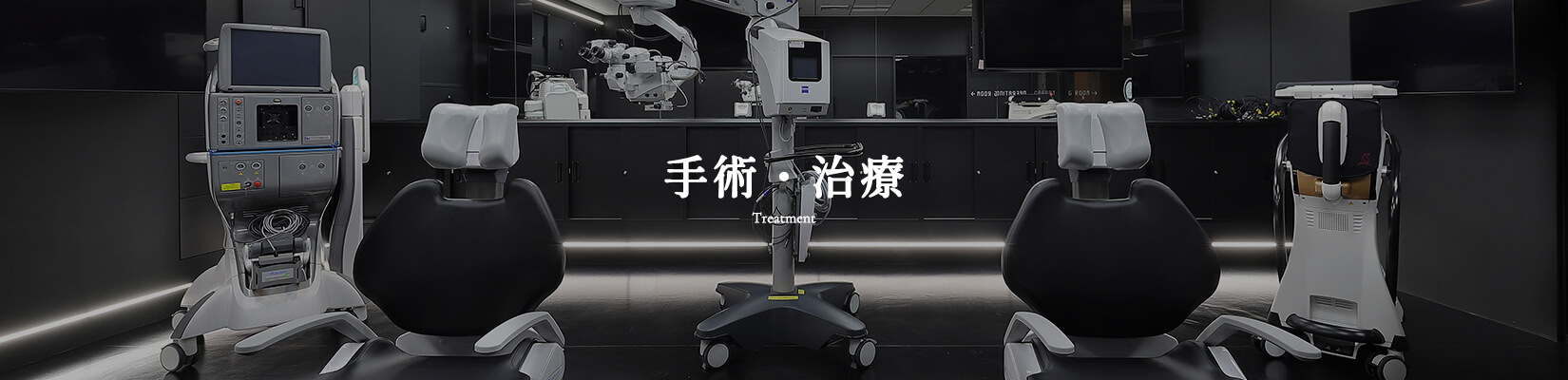

多焦点眼内レンズ
multifocal intraocular lens
白内障手術に使用する眼内レンズには大きく分けて「多焦点眼内レンズ」と「単焦点眼内レンズ」があります。患者さんの求めるライフスタイルとそれぞれの眼内レンズの特性をふまえて、眼内レンズの種類を決定します。
- ASUCAアイクリニック取扱眼内レンズ一覧
- 多焦点眼内レンズとは
- 多焦点眼内レンズと単焦点眼内レンズとの比較
- 多焦点眼内レンズのメリット・デメリット
- 多焦点眼内レンズの種類と構造
- 選定療養と自由診療について
- 多焦点眼内レンズ使用時の注意事項
- 当院の白内障手術について
- まとめ:あなたに合った眼内レンズの選択
- 関連ブログ記事へのリンク
ASUCAアイクリニック取扱眼内レンズ一覧
多焦点眼内レンズ・焦点拡張眼内レンズ
レンズの名前をクリックすると各レンズの情報に移動します。
 Lentis Mplus
Lentis Mplus
レンティスMplus IC8
IC8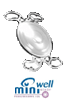 Miniwell Ready
Miniwell Ready
ミニウェル RayOne trifocal
RayOne trifocal
レイワン トリフォーカル ALSAFIT FOURIER
ALSAFIT FOURIER
アルサフィット フーリエ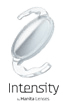 Intensity
Intensity
インテンシティー FINEVISION HP(POD F GF)
FINEVISION HP(POD F GF)
ファインビジョンHP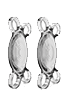 Artis Symbiose MID/PLUS
Artis Symbiose MID/PLUS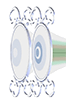 Mini WELL PROXA
Mini WELL PROXA
ミニウェル プロクサ TriDiff
TriDiff
トライディフ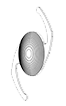 Acriva Trinova Pro C
Acriva Trinova Pro C
アクリバ トリノバ プロC-
 TECNIS Multifocal IOL
TECNIS Multifocal IOL
テクニスマルチフォーカル 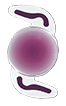 RayOne EMV
RayOne EMV
レイワン EMV TECNIS Symfony
TECNIS Symfony
テクニスシンフォニー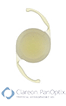 Clareon PanOptix
Clareon PanOptix
クラレオン パンオプティクス TECNIS synergy
TECNIS synergy
テクニスシナジー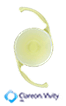 Clareon Vivity
Clareon Vivity
クラレオン ビビティー-
 ArtIOLs
ArtIOLs
アートアイオーエル -
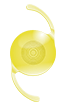 Vivinex Gemetric/plus
Vivinex Gemetric/plus
ビビネックスジェメトリック/プラス -
 Tecnis Odyssey
Tecnis Odyssey
テクニスオデッセイ -
 RayOne Galaxy
RayOne Galaxy
レイワンギャラクシー -
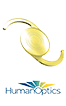 TRIVA
TRIVA
トリバ -
 TECNIS PureSee
TECNIS PureSee
テクニス ピュアシー 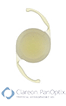 Clareon PanOptix Pro
Clareon PanOptix Pro
クラレオン パンオプティクス プロ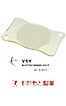 Acriva Trinova Pro
Acriva Trinova Pro
アクリバ トリノバ プロ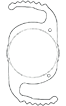 Autofocus Pro
Autofocus Pro
オートフォーカルプロ IC8 Apthera
IC8 Apthera
IC8 アプテラ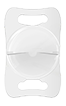 LENTIS Mplus X
LENTIS Mplus X
レンティス MPlus X
保険収載眼内レンズ
レンズの名前をクリックすると各レンズの情報に移動します。
多焦点眼内レンズとは
多焦点眼内レンズ(Multifocal Intraocular Lens:MIOL)とは、白内障手術の際に混濁した水晶体を取り除いた後に挿入する人工レンズの一種です。通常の単焦点眼内レンズと異なり、近距離・中距離・遠距離の複数の焦点を持つよう設計されています。
白内障は年齢とともに水晶体が混濁する疾患で、視力低下や色の識別が困難になるなどの症状が現れます。白内障手術では、この混濁した水晶体を取り除き、眼内レンズを挿入することで視力を回復させます。
多焦点眼内レンズの最大の特徴は、手術後に「老眼鏡や遠近両用メガネへの依存度を大幅に減らせる」という点です。日常生活の様々な距離での視力をカバーできるため、QOL(生活の質)の向上に大きく貢献します。
多焦点眼内レンズと単焦点眼内レンズとの比較
| 多焦点眼内レンズの特徴 | 単焦点眼内レンズの特徴 | |
|---|---|---|
| 焦点距離 | 複数の距離(遠方・中間・近方)にピントが合う | 1つの距離(通常は遠方)にのみピントが合う |
| 保険適用 | 差額は自己負担(選定療養または自由診療) | 健康保険が適用される |
| コスト | 単焦点より高額 | 比較的安価 |
| 視力の質 | 複数の距離で見えるが、コントラスト感度がやや低下する場合がある | 設定した距離では鮮明な視界が得られる |
| 術後 | メガネ依存度が大幅に減少 | 近方視のために老眼鏡が必要になることが多い |
多焦点眼内レンズのメリット・デメリット
| 多焦点眼内レンズのメリット |
|
|---|---|
| 多焦点眼内レンズのデメリット |
|
多焦点眼内レンズの種類と構造
多焦点眼内レンズには大きく分けて以下の種類があります。
屈折型多焦点眼内レンズ
レンズ表面に同心円状の屈折領域を持ち、光の屈折を利用して複数の焦点を作り出します。屈折型は一般的に中間距離の視力が優れています。
回折型多焦点眼内レンズ
レンズ表面に微細な回折輪を持ち、光の回折現象を利用して複数の焦点を形成します。近方視と遠方視のコントラストが良好な傾向があります。
ハイブリッド型多焦点眼内レンズ
屈折と回折の両方の特性を組み合わせたレンズで、より広い範囲の焦点距離をカバーします。各距離でのバランスの取れた視力を提供します。
調節型眼内レンズ
眼の筋肉の動きに反応して位置や形状が変化し、自然な調節能力に近い機能を提供するレンズです。技術的にはまだ発展途上の部分もあります。
焦点深度拡張型(EDOF型)眼内レンズ
Extended Depth of Focus(焦点深度拡張)型は、特殊な光学設計により単一の焦点を引き伸ばすことで、より広い範囲の視力をカバーします。従来の多焦点レンズと比較して光の分散が少なく、ハロー・グレアなどの光視症状が軽減される傾向があります。ただし、特定距離のコントラストが不良な場合がある。
ピンホール型眼内レンズ
小さな穴(ピンホール)の原理を応用したレンズで、中心部に微小な穴が開いた構造になっています。このピンホール効果により焦点深度が拡大し、近距離から遠距離までの視力向上が期待できます。また、光の散乱を抑える効果もあり、術後の光視症状が比較的少ないという特徴があります。特に角膜不正乱視などの特殊な症例にも効果を発揮する場合があります。
トーリック多焦点眼内レンズ
乱視矯正機能を持つ多焦点レンズで、乱視がある患者さんにも多焦点の恩恵を提供できます。
各レンズの構造は精密に設計されており、光学的特性や生体適合性を考慮して製造されています。レンズ素材としては、アクリルやシリコンなどが使用され、紫外線カット機能を持つものも多くあります。
選定療養と自由診療について
多焦点眼内レンズの費用には、保険適用部分と保険適用外部分があります。その費用体系は以下のように分かれています。
選定療養とは
選定療養制度は、保険診療と保険外診療を併用できる制度です。白内障手術自体は保険適用ですが、多焦点眼内レンズの差額分は患者さんの自己負担となります。
- 保険適用部分: 白内障手術の基本費用(手術料、検査料、入院費など)
- 自己負担部分: 多焦点眼内レンズと単焦点眼内レンズ、検査代の差額
費用の目安
- 選定療養での多焦点眼内レンズ: 片眼あたり約15〜50万円の追加費用
- 自由診療での多焦点眼内レンズ手術: 片眼あたり約30〜90万円の総費用
※正確な費用は医療機関や選択するレンズの種類によって異なります。詳細は当院までお問い合わせください。
自由診療との違い
自由診療は全額が保険適用外となる診療形態です。一部の高度な多焦点眼内レンズや特殊な手術方法は自由診療になる場合があります。
多焦点眼内レンズ使用時の注意事項
多焦点眼内レンズを最大限に活用し、満足度を高めるためには以下の点に注意が必要です。
術前の注意事項
- 適応の確認: 角膜疾患や網膜疾患がある場合は適応外となる可能性があります
- 期待値の調整: 完璧な視力回復ではなく、メガネ依存度の軽減が主目的であることを理解する
- 生活スタイルの考慮: 読書や運転など、主に行う活動に適したレンズを選択する
術後の注意事項
- 適応期間の理解: 脳が新しい視覚に慣れるまで3〜6ヶ月程度かかることがある
- 定期検診の重要性: 術後の経過観察は視力安定のために必須
- ドライアイへの対処: 人工涙液の使用など適切なケアが必要
- 光視症状への対応: ハロー・グレア(夜間の運転で車のライトが反射したりにじんで見えたりする現象)は時間とともに軽減することが多い
- 眼鏡の補助的使用: 特定の作業では補助的に眼鏡が必要になる場合もある
長期的な注意点
- 定期的な眼科検診: 後発白内障や他の眼疾患の早期発見のため
- 明るさ対策: クリアなレンズに切り替わるため、最初眩しく感じる方
- 生活環境の調整: 必要に応じて照明を調整するなど、視環境を整える
当院の白内障手術について
当院では患者さま一人ひとりの目の状態や生活スタイルに合わせた最適な白内障手術を提供しています。
手術の特徴
- 最新の手術設備: 精密な手術を可能にする最先端の医療機器を導入
- 豊富な実績: 年間多数の白内障手術を実施する経験豊富な医師が担当
- 多様なレンズ選択肢: 各メーカーの様々なタイプの多焦点眼内レンズを取り扱い
当院の手術プロセス
- 詳細な検査と診断: 術前に目の状態を細かく評価
- 丁寧なカウンセリング: 患者さまの希望や生活スタイルを考慮したレンズ選択のご提案
- 精密な手術: 小切開で行う低侵襲手術
- 充実した術後ケア: 定期的な経過観察と必要に応じたアフターフォロー
患者さまの満足度向上への取り組み
- 術前シミュレーション: 視力改善効果の予測
- 術後サポートプログラム: 視覚適応をサポートするトレーニングのご案内
- 医療相談窓口: 不安や疑問にいつでも対応
まとめ:あなたに合った眼内レンズの選択
多焦点眼内レンズは、適切に選択され使用されれば、白内障手術後の生活の質を大きく向上させることができます。しかし、すべての方に適しているわけではありません。
最適なレンズ選択のためには、以下の点を総合的に考慮することが重要です。
- 1. 生活スタイルと視力ニーズ: 読書、パソコン作業、運転、スポーツなど主な活動
- 2. 予算: 費用面での制約と長期的なメリット
- 3. 目の健康状態: 他の眼疾患の有無や角膜状態
- 4. 期待値: 現実的な視力改善の目標設定
当院では、これらの要素を総合的に評価し、患者さま一人ひとりに最適な眼内レンズをご提案しています。多焦点眼内レンズに関するより詳しい情報や個別のご相談は、お気軽に当院までお問い合わせください。
白内障は早期発見・早期治療が重要です。定期的な眼科検診を通じて、最適なタイミングでの治療をご検討ください。
関連ブログ記事へのリンク
野口三太朗医師の監修する最新エビデンスを元にしたブログ記事です。
その他、多数の記事がございますのでご覧ください。https://asuca-eye.com/blog_doctor/
- ●モノビジョン(左右のターゲットをずらした眼内レンズ移植)第一部:基礎理論と分類 👁️✨
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/09/16/2951/ - ●モノビジョン(左右のターゲットをずらした眼内レンズ移植)第二部:臨床成績と最新技術 📈🔬
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/09/16/2964/ - ●多焦点眼内レンズを抜去交換する原因について 👁️💊
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/09/08/2940/ - ●多焦点眼内レンズ(多焦点IOL)で後悔する原因と眼科医選びの重要性 👁️
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/08/18/2842/ - ●白内障手術における眼内レンズ選択の真実 – 日本のプレミアム眼内レンズ普及率の謎「高いから単焦点レンズにする」のウソホント 🔍
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/08/04/2820/ - ●アスカアイクリニックの白内障手術における乱視矯正の実績 😊✨
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/07/28/2803/ - ●眼内レンズ交換に関する正確な情報の重要性
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/03/17/1965/ - ●新しい眼内レンズ(多焦点など)が必ず優れているわけではない
https://asuca-eye.com/blog_doctor/2025/01/20/1618/
院内倫理委員会の設置
当院では院内倫理委員会を設置しております。弁護士1名、外部企業者4名の5名にて構成されております。いずれの未承認デバイスについても、院内倫理委員会承認を得られたものを使用しております。